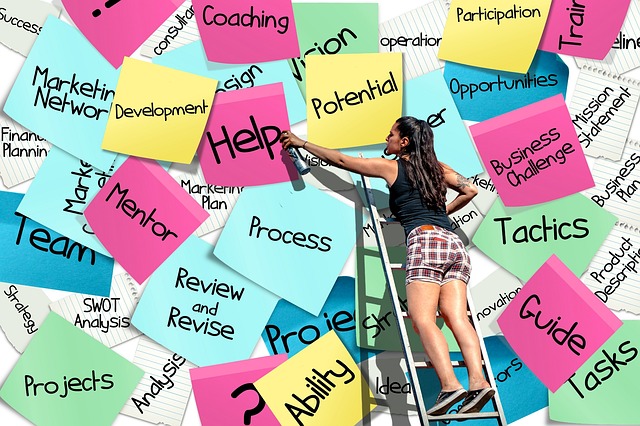- 組織で働く人で改革を行いたい人
- 課題、問題を迅速に解決したい人
- 戦略的に物事を考え推し進めたい人
- 新しい商品やサービスをどんどん生み出したい人
この記事では、上記のような「成功へと導く考え」を手に入れたい方を対象に書いています。
そのために、これから説明する「7つのリスト」を手に入れる必要があります。
下記の書籍「考える力をつける9つのステップ」から、人生の成功を手に入れるために必要な「アイデア」を生み出す道具となる「7つリスト」について紹介します。
それでは、早速リストを1つずつ説明していきます。
もくじ
1.組織にイノベーションを起こせる人になるための「3つの意識」
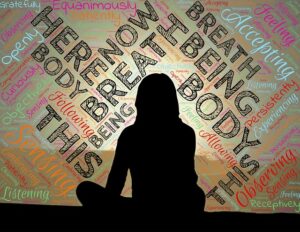
3つの意識
1つ目のリストは、「3つの意識」です。
- 問題意識
- 当事者意識
- 危機意識
この「3つの意識」を持つことにより、他の人が持っていない意識が持てるようになります。
つまり、これまで何も意識していなかったことに対して、多くの気づきをもたらしてくれます
それでは、それぞれの意識について説明します。
1.問題意識
問題意識とは、「あらゆるものになぜという問いかけすること(WHY思考)を習慣にして現状に素朴な疑問を持つこと」です。
常日頃から全てのことに、問題意識を持つ必要があります。
例えば、「なにげなくやっているこの手順で本当に正しいのか?」という意識を持つことにより、さらに良い手順に変えるチャンスを与えてくれます。
問題意識すら持っていないと、そのチャンスがあることすら気がつかずに過ぎ去っていきます。そういう問題意識を持つだけで、持っていない人より1歩も2歩もリードすることができます。
2.当事者意識
当事者意識とは、「すべての課題に対して、自分自身の課題として捉え改善策を模索すること」です。
先程の「問題意識」を持てたとして、「このようにするべきだ、このように直すべきだ」などと評論家のごとく言っているだけだと、ただの口うるさいだけの人になり、周りの人から煙たがられます。そして、人がドンドン離れていきます。
そうならないためにも、「問題意識」を持ってドンドン発言し、「当事者意識」を持って自ら率先して改革を実行する人になれば、周りの人はドンドン集まってきます。そして、人望を手に入れることができます。
また、他人がやってしまった失敗やミスに対して、自分のこととして捉えることにより、自分も同じ失敗やミスを起こさないようにすることができます。
3.危機意識
危機意識とは、「現状を放置することで発生するリストを察知すること」です。
最後の「危機意識」は、現状に甘んずることなく常にいろいろな危機がやってくることや思わぬリスクが発生することを意識することです。
そして、十分な対策を打っておくことにより、実際にそうなった場合に最小の被害で乗り越えることができます。
2.改善や革新するための具体的な「7つの問題意識」

問題意識
2つ目のリストは、「7つの問題意識」です。
- なぜそんなに「値段が高い」のか?
- なぜそんなに「故障が多い」のか?
- なぜそんなに「品質が悪い」のか?
- なぜそんなに「苦情が多い」のか?
- なぜそんなに「時間がかかる」のか?
- なぜそんなに「手直しが多い」のか?
- なぜそんなに「手続きが煩雑」なのか?
「7つの問題意識」は、先程の「3つの意識」の1つである「問題意識」を具体的にどういう視点で考えるのかを表しています。
あらゆることに、なぜなぜを持つことにより、さらに良い状態を作り出すことができます。
普段やっている作業やその手順、成果物に対して、7つの問題意識を当てはめてみると良いです。
そうすることにより、今までなんとも思っていなかったことに対して、問題を見つけることができ改善・改良のアイデアが湧き出してきます。
3.問題解決への「5つのステップ」

問題解決
3つ目のリストは、問題解決への「5つのステップ」です。
その「5つのステップ」は以下です。
- 問題発見
- 分類と整理
- しぼり込み
- 優先順位づけ
- 解決の提案
問題意識を持った瞬間からいろいろな問題・課題がでてきます。
そういう問題や課題を迅速に解決させるためのステップとなっています。
当事者意識を持った改革リーダーとしては、迅速に最小の労力でたくさんの問題・課題を解決することが期待されます。
それでは、それぞれのステップについて説明します。
1.問題発見
問題発見とは、「問題を洗いざらい列挙してみること」です。
いろいろな角度から見て、考え、すべての問題を挙げてみましょう。
このステップでは、1つの問題に対して改善方法や解決方法を考えるのではなく、あらゆる問題と思えるものをもれなく挙げます。
これはいいかなと思うものも、考えずに挙げ切ります。
2.分類と整理
分類と整理とは、「問題をテーマ別に分類し、整理すること」です。
同じような問題・課題同士をテーマ別にグループ分けしましょう。
グループ分けすることにより、このあとのステップでまとめて対応ができるようになるからです。
そのためにも、分類しておくことが重要になってきます。
また、整理とは「必要なもの」と「不要なもの」に分けて、「不要なもの」を捨てることです。
数ある問題のうち、どうやっても、解決できないものがあります。
そういう問題は、悩んでいる時間がもったいないので、捨てましょう。
それ以外の問題に対して、集中できるようにしましょう。
3.しぼり込み
しぼり込みとは、「テーマ毎に分類した問題のうち、今回対応するものを絞ること」です。
すべての問題を一気に解決できれば、それが一番良いのですが、現実的には無理なことが往々にしてあります。
また、今は無理だけど、時期をズラせば解決できることもあります。
そういった事を考慮して、今対応するべき問題をしぼり込み、限られた時間のなかでより良い成果を出せる状態を作りましょう。
4.優先順位づけ
優先順位づけとは、「判定基準を設け、優先順位を決めること」です。
テーマ毎に分類した問題のうち、どの問題から対応するか判断しましょう。
その判断基準は、状況に応じて変える必要があります。
判断基準の例は、以下です。
- 解決することにより効果が高いもの
- すぐに解決ができそうなもの
- 安く解決できそうなもの
そういった判断基準を決めて、どの問題から対応するか決めます。
また、テーマ毎の問題のなかから、どの問題から先に対応するかも決めましょう。
5.解決策の提案
解決策の提案とは、「優先度の高い順に、具体的な解決策を講じること」です。
つまり、最後のステップでやっと問題に対して実際の対応をとることです。
これまでのステップ4までが、準備段階となっていました。
よく言われている「仕事は準備が8割」ということです。
要するに、準備がものすごく重要ということ。
準備さえしっかりやっておけば、その仕事の8割は終わったようなものということです。
余談その1
新人の頃に、仕事ができる先輩に言われた言葉があります。
その言葉は、今でも覚えています。
「仕事ができるようになりたかったら、準備をしっかりやることだ。準備をおろそかにする奴は、たいした仕事はできない。」
その当時は、計画を立てたり、設計書を作成することは時間の無駄なことと思っていました。
プログラミングしないことには、システムは完成しないから、そういう風に考えていました。
つまり、システムを完成させる準備とは、計画を立てて、設計書を作成することです。
「そういう準備をおろそかにする奴は、ろくなシステムは作れないよ」と言われたので、すごくショックを受けました。
自分が重要視しないといけないものが、真逆だったからです。
実際に、設計を適当にやってプログラミングすると、プログラミングしている最中に課題がでてきて、なかなか進捗しないことが多々ありました。
準備をしっかりやっておけば、あとは決めた通りにプログラミングするだけなので、予定通りにシステムを完成させることができました。
4.物事を成功へと導く「3つの戦略思考」

戦略思考
4つ目のリストは、「3つの戦略思考」です。
- 俯瞰思考
- 水平思考
- 垂直思考
この4つ目のリストは、「なにかを達成するためにどうやって進めるか」を思考するときに役立てます。
例えば、あるプロジェクトを任されたときに、「決められた予算・決めれた期限・決められた要員」で達成するにはどうするかを考えないといけない時などに利用できます。
それぞれについて、説明します。
1.俯瞰思考
俯瞰思考とは、「全体的な状況を広く見渡すこと」です。
つまり、鳥のように高い空から地上を見渡すように全体を見て、考えることです。
先程の例でいうと、プロジェクト全体を俯瞰して、まずは全体をつかむ必要があります。
全体を俯瞰して、以下を思考します。
- 何をする必要があるか
- いつまでに何をやるか
- ゴールをどこにするか
ザックリいうと、ゴールまでにやる必要がある作業リストを出すことです。
2.水平思考
水平思考とは、「考えれる多くの選択肢を出し切ること」です。
つまり、可能・不可能は置いておいて、挙げれるだけ選択肢を出すことです。
出し切った選択肢は、このあと説明する「垂直思考」で取捨選択をするのでこの段階では、選択肢を捨てずに出しましょう。
先程の例でいうと、「俯瞰思考」で出した作業リスト1つ1つに対して、考えれるやり方の選択肢を出します。
具体的には、以下を思考します。
- どういう手順でやるか
- どういう順番でやるか
- 誰がやるか
ザックリいうと、各作業のやり方の選択肢を出します。
3.垂直思考
垂直思考とは、「深く掘り下げて検討すること」です。
つまり、先程の「水平思考」で出した多くの選択肢からどれを選ぶかを検討します。
1つ1つの選択肢のメリット・デメリットを出し、総合的に良いと判断できるものを選択します。
先程の例でいうと、「水平思考」で出した多くの選択肢からどれを選択するか検討します。
具体的には、以下を思考します。
- どういうメリットがあるか
- どういうデメリットがあるか
- どういうリスクがあるか
- そのリスクをどうやって回避するか
- どの程度の資源が必要か
ザックリいうと、各作業のやり方を一番良い組み合わせで選択します。
数多くの選択肢のなかから、どれを選び、どの程度の人や資源をそこに投入するか。
それを考えることが戦略であり、「選択と集中」です。
つまり、限られた時間・資源のなかで効率よく物事を進め、最大の結果を出すかを思考することです。
余談その2
新人の頃に、先輩に以下のことをよく言われていました。
その言葉は、今でも覚えています。
- 「対応方法は最低でも3つ以上出してから、検討しなさい」
- 「よく検討もせずに選択肢1つで物事を進めてはいけません」
- 「ありえないと思うような案も気にせず出し、出したあとの検討のときに削除しなさい」
実際に自分で案を検討するときに、気づいたことがあります。
それは、「案を出す作業」と「出した案を検討する作業」を同時にしてはいけないことです。
なぜなら、人は同時にいろいろなことをすると、効率が大きく下がってしまうからです。
わかりやすい例でいうと、プログラミングしながら設計することです。
別々に作業をやった場合を1とすると、同時にやった場合は3以上になります。
また、同時にやった場合は、1つ1つのパーツ毎に設計することになるので、全体を組み合わせたときに矛盾が発生する場合が多いからです。
同時に作業をすると、品質が明らかに下る結果となります。
5.デカルトがすすめる「物事を考えるときの4つの態度」

態度
5つ目のリストは、「物事を考えるときの4つの態度」です。
- 自分が明らかに正しいと認めたこと以外は、「真」と認めないこと
- 検討し吟味する問題は、できるだけ小さく分けて考えること
- 思想は順序に従って、形成すること
単純なものから段階を踏み、複雑な認識に至ること- 常に見落としがないように、全体を見て、詳細に記述すること
この「物事を考えるときの4つの態度」は、先程の「戦略思考」で考え出した選択肢から最良の選択をするときに使える態度となっています。
それでは、1つずつ「4つの態度」について説明します。
1.自分が明らかに正しいと認めたこと以外は「真」と認めない
端的にいうと、「人のウワサを簡単に信じるな」ということです。
人から聞いた情報を全て鵜呑みにせず、自分の目で見て、直接聞いたことだけを信じましょう。
人から聞いた情報は、どこかでねじ曲がっていたり、聞いた人の都合良く受け取ったりして、真実と異なっている可能性があるからです。
2.検討し吟味する問題は、できるだけ小さく分けて考えること
端的にいうと、「なにかを考えるときは、対象を小さく分けて考えましょう」ということです。
複雑に絡み合った問題を一気に解決しようとせず、最小単位に細分化してから検討しましょう。
例えば、ブログ記事を書く作業について検討してみましょう。
ブログ記事を書くという作業を、どこから考えたら良いかいろいろ迷うと思います。
まず、以下のように作業を細分化してから、検討しましょう。
- どんなテーマで記事を書くか?
- 記事のタイトルをどうするか?
- 各見出しをどうするか?
- アイキャッチ画像はどうするか?
- などなど
対象を細分化することにより、考えないといけないことが明確になりました。
思考があっちこっちにいかなくなり、的を絞れる状態を作って考えましょう。
3.思想は順序に従って形成すること
端的にいうと、「考える順番は重要です」ということです。
重要なことから考え始めないと、考えたことが無駄になる可能性があるからです。
些細なことを先に考え、最後に一番重要なことを考えた場合、最手段になってそれまで考えて決めたことをくつがえす結果になるかもしれないからです。
例えば、先程の「ブログ記事を書く作業」を間違った順番で考えるとわかりやすいです。
アイキャッチ画像を決めたあとに、どんなテーマで記事を書くか検討したとします。
「考えたテーマ」と「決めたアイキャッチ画像」が合わなかったら、またアイキャッチ画像を検討する必要があります。
明らかに検討する順番が悪いです。
このようにならないためにも、重要なことから順番に考えるようにしましょう。
4.常に見落としがないよう全体を見て、詳細に記述すること
端的にいうと、「すべてのことを一度テーブルに並べましょう」ということです。
些細な問題だから検討する必要がないとして捨てずに、一旦はすべての問題を書き出して検討しましょう。
なぜなら、些細な問題と思っていたことが、実はとても重要なことだったということが往々にしてあるからです。
すべて書き出して検討した上で、必要のない問題は捨てましょう。
また、各問題についても、曖昧に書かず、詳細になにが問題か誰が見てもわかるように書き出しましょう。
なぜなら、曖昧に物事を捉えてしまうと、間違った答えを導き出してしまう可能性があるからです。
そうならないためにも、正しく問題に向き合えるように、詳細に問題を書き出しましょう。
6.クランボルツがすすめる「偶然をチャンスとして活かせる人の5つの条件」

条件
6つ目のリストは、「偶然をチャンスとして活かせる人の5つの条件」です。
- 好奇心があること
- 持続性があること
- 柔軟性があること
- 楽観性があること
- 冒険心があること
このリストは、これまでのリストとは異なり、偶然に起きたことからチャンスを掴める人になるために必要な条件となっています。
「クランボルツ」とは、「計画的偶発性理論」を提案した心理学者です。
「計画的偶発性理論」とは、人の人生は偶然な出来事によって多くが変わる。
その偶然を計画的に起こして、人生をより良いものにしようという考え方です。
詳細は、以下を参照してください。
参考 ジョン・D・クランボルツWikipedia
それでは、1つずつ「偶然をチャンスとして活かせる人の5つの条件」について説明します。
1.好奇心があること
好奇心があるとは、「より良いもの、面白いものを見つけようとする特性」です。
いろいろなことに、常にアンテナを張り、何からでも学ぼうとする姿勢が必要です。
2.持続性があること
持続性があるとは、「高いレベルに目標を設定して、興味を継続させられる特性」です。
「イチロー選手」をイメージすると「持続性があること」の重要性がわかりやすいです。
技術レベルが高いことも重要ですが、努力を高いレベルで持続させれることがもっと重要ということです。
そういった持続性があったことで、「イチロー選手」は長い間、一流選手として活躍することができたのでしょう。
自らの目標を持ち、現状に満足することなく、常に進化しようとする姿勢が必要です。
昨日の自分より、今日の自分はさらに進化しているようにする。
そして、今日の自分より、明日の自分はもっと進化しているようにしましょう。
3.柔軟性があること
柔軟性があるとは、「自分の固定観念を、客観的に捉え直すことができる特性」です。
固定観念をもっているために、新しい発想やアイデアが生み出しにくくなっています。
そうならないためにも、「柔軟性」が重要となります。
また、新しい仕組みも積極的に取り入れようとすると、また違った発想やアイデアが浮かぶチャンスが増えます。
外からの刺激によって、人の脳は活性化されます。
難しいのですが、自分の固定観念を捨て、新しいことを受け入れる姿勢を持ちましょう。
今知っていることや、世間では常識とされていることなど、何も考えずに当たり前として受け入れていることに対して、常に「なぜ?どうして?」という気持ちで、柔軟に対応できるようになりましょう。
4.楽観性があること
楽観性があるとは、「物事のプラスとマイナスの両面を理解し、プラスに意識を保つことができる特性」です。
「楽観性」は、起こる出来事に対して、プラス思考で受け入れる姿勢を持つことです。
嫌なことが起きたときでも、そこから何かを学び取ろうとする力です。
被害者意識を持たず、自分に足りない何かを学ばせようとして起こっているのだと考えましょう。
何事に対しても楽しめる姿勢を持てれば、最強になれます。
5.冒険心があること
冒険心があるとは、「変化を恐れず、むしろ変化にチャンスを見い出そうとする特性」です。
人は基本的に、変化を嫌う生き物です。
しかし、「冒険心」を持って変化を恐れず、凝り固まった現実に改革を起こせる人になりましょう。
そうすれば、いろいろな困難なことに向き合わないといけなくなりますが、その代わりにいろいろな経験を積むことができます。
その経験を生かして、また新しいことにチャレンジできるようにつなげれば、もっと大きなチャンスを掴めるかもしれません。
偶然に起こる出来事に対して、逃げず最善をつくそうとする姿勢が成功や幸福をたぐり寄せます。
「その幸運は、偶然ではないのです!!」
7.オズボーンがすすめる「新しいアイデアを生み出す9つのチェック項目」

チェック項目
7つ目のリストは、「新しいアイデアを生み出す9つのチェック項目」です。
- ほかに使い道はないか(転用)
- ほかからアイデアを借りられないか(応用)
- 変えてみたらどうか(変更)
- 大きくしてみたらどうか(拡大)
- 小さくしてみたらどうか(縮小)
- ほかのもので代用できないか(代用)
- 入れ替えてみたらどうか(置換)
- 逆にしてみたらどうか(逆転)
- 組み合わせてみたらどうか(結合)
このリストは、新しい手順や商品・サービスを生み出すときに役立つ、アイデアを生み出すきっかけを与えてくれます。
「オズボーン」とは、「ブレインストーミング」を考案した人です。
「ブレインストーミング」とは、複数の人で新しいアイデアを生み出す会議方法です。
いろいろな考えから、より良いアイデア生み出すときに使えます。
詳細は、以下を参照してください。
参考 ブレインストーミングWikipedia
新しい考えは、「古くからある考え」の組み合わせだったり、違う場所に置いた「古くからある考え」だったりします。
例えば、新しく書かれた本は、先人が書いた本から得た情報を組み合わせて発想したアイデアについて、書かれていたりします。
人がゼロからアイデアを生み出すことは、難しいものです。
しかし、すでに存在するアイデアを、応用したり、転用することによって、新しいアイデアを生み出すことはそう難しいことではありません。
わかりやすい例でいうと、最新のスマートフォンです。
携帯電話とカメラ、アプリケーションを組み合わせて、作られています。
スマートフォンの進化は、まさに古いアイデアを応用して出来上がっております。
それでは、1つずつ「偶然をチャンスとして活かせる人の5つの条件」について説明します。
1.ほかに使い道はないか(転用)
「転用」とは、本来の目的をほかに変えて使用することです。
ペットポトルを他に使えないか?
2.ほかからアイデアを借りられないか(応用)
「応用」とは、得た知識を他の分野のことがらに当てはめて用いることです。
仕事で習得した交渉術を、お小遣い値上げ交渉に応用する。
3.変えてみたらどうか(変更)
「変更」とは、決められた物事などを変えることです。
今まで、A地点へ電車で行っていたのを、他の移動手段に変更する。
4.大きくしてみたらどうか(拡大)
「拡大」とは、広げて大きくすることです。
A4サイズで作成していたビラを、A3サイズに拡大してみる。
5.小さくしてみたらどうか(縮小)
「縮小」とは、縮めて小さくすることです。
A4サイズで作成していたビラを、A5サイズに縮小してみる。
6.ほかのものを代わりに使えないか(代用)
「代用」とは、あるものに代えて、別のものを使うことです。
お菓子の袋を、ゴミ箱に代用する。
7.入れ替えてみたらどうか(置換)
「置換」とは、置き換えることです。
ビラの文字色を置き換えてみる。
タイトル文字色を寒色系から暖色系に置き換えてみる。
本文の文字色を、暖色系から寒色系に置き換えてみる。
8.逆にしてみたらどうか(逆転)
「逆転」とは、それまでとは反対の方向に回転することです。
時計の針の進行方向を、逆転させてみる。
9.組み合わせてみたらどうか(結合)
「結合」とは、2つ以上のものを結びつけて1つにすることです。
携帯電話とデジタルカメラを結合してみる。⇒カメラ付き携帯
明日からのアイデア量産活動に、「オズボーンの9つのチェック項目」を活用してみてはいかがでしょうか。
また、部下や後輩に「オズボーンの9つのチェック項目」を紹介すれば、勝手に良いアイデアを生み出してくれるかもしれません。
他には、「ブレインストーミング」を利用して、アイデア発想会議をしてみても良いかもしれません。
今回の「7つのリスト」は、いかがでしたか?
この「7つのリスト」を使って、自らを成功へと導くアイデアを生み出してみましょう。
同じ著者の他の本には、以下もあります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事をシェアしていただけると喜びます。
 くうねるの本から自分改革
くうねるの本から自分改革